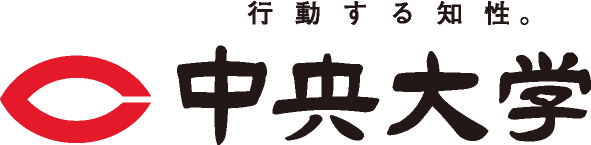【特別対談】
社会経済学科 小尾晴美先生
働くことは生きること。
2つの経済学の視点から「労働問題」をひも解く
経済学と社会経済学という異分野で活躍する二人の研究者が、それぞれの視点で「労働問題」の解決法を語り合いました。
経済学から見る労働問題とは?
阿部:
経済学部では、労働問題を経済学の視点から研究します。たとえば賃金がどう支払われているか、なぜ人によって差があるのか、最低賃金はどんな影響を与えているのかなど、身近な問題を扱います。労働問題には堅苦しく重いイメージがあり、高校生には縁遠く感じるかもしれませんが、人は生きていくためには働かねばならないもの。ですから、労働にまつわる問題に興味をもってほしいと思います。
小尾:
おっしゃる通り、多くの人が人生のほとんどの時間を労働に費やすことになります。私は元々人間に対する興味が強かったので、一人ひとりの生き方に大きく関わる労働、特に職場・社会・日本の枠組みで人々がどのように働いているかというテーマに自然と興味を持ちました。私も含め多くの人が働いていますし、家族のケアや家事も「対象に働きかけて変化させる」という意味で労働に含めることができます。働くことはすなわち生きることと言えるのではないでしょうか。

阿部:
大多数の人が学校を卒業後、4、50年働くことになります。これほど長い時間を費やすにもかかわらず、労働問題を重視しない人もいますよね。特に学生は就職活動やキャリア形成に興味があっても、働くこと自体には興味を示さないことが多い。社会人でも労働環境の改善に関心を持たない方もいます。このような状況を直視し、環境の改善や問題の要因について問いを立て、課題解決をめざして考えることこそが、労働問題を研究する面白さです。
2つの「経済学」のアプローチについて教えてください。
阿部:
経済学科で扱う労働経済学は、労働市場のメカニズムを解明するために、ミクロ経済学やマクロ経済学をベースにして研究が進んできた分野です。ミクロ経済学は個人や企業の行動を、マクロ経済学は国全体の経済の動きを分析対象としています。データを使って分析するだけでなく、ミクロ・マクロ経済学の理論を使って、政府の政策や市場介入の効果測定、それらの有効性の検討を目的としています。私の最近の主なテーマは最低賃金、長時間労働の問題や失業などですね。
小尾:
社会経済学では、制度や市場の仕組みに加え、経済活動以外の人々の営みや、政府・思想家の考え方も分析の対象とし、経済現象を多面的に捉えます。質的データや制度史的アプローチを組み合わせる点が、経済学科とは異なります。ただ、先ほど阿部先生がご説明された労働経済学の目的は、社会経済学の目的でもあります。アプローチは違ってもゴールは共通していますね。

阿部:
分析対象はほとんど同じでも、研究方法によって見え方が変わってきます。労働問題は経済学や社会経済学に限らず、社会学や組織心理学などさまざまな分野で研究されています。その中でも経済学の最大の特徴は、ミクロ・マクロ経済学の理論に基づいて分析を行う点にあります。また、社会経済学と比べると、全体を捉えてから個別の事象を見ていく演繹的な方法を取る傾向がありますね。
小尾:
反対に、社会経済学科では個別から全体へというアプローチが多いです。個々の事例の調査を積み上げることで、帰納法的に大きな事象の説明を試みます。
ただし、必ずしもこのアプローチを取るとは限らず、経済学科と同様に全体の把握を重視する考え方の先生もいらっしゃいます。例えば、政府や企業による賃金の分配や、税制や社会保障という形での再分配など、社会政策全体を捉える視点もあります。
阿部:
経済学で解決できないことが社会経済学で解決できる、あるいはその逆もあるでしょう。例えば障がい者雇用の問題においては、障がいが軽度で働ける人の課題は、市場メカニズムなど経済学の枠組みで考えることができます。一方で、働くことが難しい人もいます。その場合でも社会とのつながりを重視して就労の場を作ろうとするなら、環境づくりや支援の仕組みは社会政策の領域になります。
経済学は効率を重視しますが、ケアのように人との関わりを大切にする分野では、効率だけを求めるべきではありません。
小尾:
社会の変化に伴って、経済学だけでは解決できない課題や、これまで見過ごされてきた問題にも目を向ける必要が生じます。社会経済学は、そうした問題の実態を明らかにし、全体像を捉える視点を提供できる分野です。
例えば1970〜80年代に長時間労働が可能だった背景には、ケアと労働が明確に分かれ、無償でケアを担う女性の存在がありました。しかし現在は労働市場の変化により、ケアを効率性だけで論じることが難しくなっています。つまり、経済の仕組みに、社会政策的な視点を組み込んでいく必要があるのです。
一方で、経済学の数理モデルや計量分析による因果検証は、政策効果などを数量的に評価するうえで依然として有効です。
阿部:
経済学で量的データを扱う身近な例として挙げられるのが、ゼミの学生が研究していた「ビニール傘は安いのか、高いのか」というテーマです。傘自体は安くても、失くす頻度を考えると、結果的には高い傘を買うよりも出費がかさむ可能性があるということです。そういった問いを立てて、ミクロ経済学の理論や手法を使って分析します。
領域による調査方法の違いとは? 研究を通じて身につく力は?
小尾:
私は、主に現場に赴く「参与観察」という方法を取っています。実際に働く人たちに交じって現場を観察したり、現場の方にインタビューをしたりすることで研究を進めています。長時間労働のような特定の事象の要因を検討するときは、複数事例の調査の蓄積を通して明らかにするプロセスが必要です。問題の背景や要因を明らかにするには、統計によって全体の傾向を把握したり、シミュレーションを行ったりすることも大切です。同時に、数字の背後にある実態や、現場で何が起きているのかを理解することが重要だと考えています。
阿部:
経済学では、主に政府や大学が収集している統計データや、民間のシンクタンクの調査データを分析材料とします。データ分析は、まずデータをどのように扱うのが最善かを考えることから始まります。得られた結果を考察し、ときには予想外の結果に直面することもありますが、その要因を探ることこそが、データ分析の醍醐味です。
将来労働問題の研究を仕事にしようという学生は少ないと思いますが、社会に出れば、どんな就職先でもデータを読み解く力やそこから何かを発見する力は重要になるはずです。

小尾:
私は集団で議論する力や、人と人をつなぐコーディネート力を育むことを重視しているので、ゼミでの活動は常に集団で行うよう指導しています。インタビュー調査では、計画立案からアポイントメントの取得、現場での対話や資料収集までの一連の過程を通じて、人とつながる力を養うというねらいがあります。AIの発達が進むことで単純な作業効率は高まっていますが、社会に出て仕事をするうえではさまざまな人とつながり、コミュニケーションを取ることが欠かせません。そうしたときに役立つ汎用的な能力を、学生時代に身につけてほしいと思っています。
阿部:
先ほどもお話したように、私の分野ではデータ分析を行うことが多いのですが、データだけではわからないことは思いのほかたくさんあります。なぜこの職場では労働時間が長いのかという疑問に対する答えはデータからは見つかりませんから、現場に行って尋ねるのです。数量的データからは全体像を掴めますが、全てをつぶさに語れないという制約もあります。メリットとデメリットを理解し、多角的な視点から状況を判断しなくてはなりません。
小尾:
私も同感で、やはりどちらの手法も必要だと思います。データだけで全てを説明できないのと同様に、個別の事例から全体を語ることも困難です。調査やインタビューを行った個別の事例や、そこから明らかになったことは、あくまでもその特定の事例においてのみ言えることで、語れることには限界があります。どちらの研究方法も重要であり、違いはどちらに軸足を置くかという点にあります。
阿部:
特に労働問題の解決には、複数のアプローチが不可欠です。労働経済と社会政策の両方の視点が欠かせませんし、データを見るだけではわからないことも、現場だけ知っていても見えてこないものもあります。いずれか一つの視点に絞るのではなく、興味のある研究方法に重きを置いて研究する形が理想的ですね。
登壇者プロフィール

阿部正浩 教授
経歴/
2017年11月 ~ 2021年10月
中央大学大学院経済学研究科 委員長
2013年4月 ~ 現在
中央大学経済学部 教授
2008年4月 ~ 2013年3月
獨協大学経済学部 教授
2011年4月 ~ 2012年3月
Visiting Scholar, School of International Relations and Pan Pacific Studies, University of California, San Diego
2007年4月 ~ 2008年3月
獨協大学経済学部 准教授
2002年4月 ~ 2007年3月
獨協大学経済学部 助教授
2006年9月 ~ 2007年1月
参議院 客員調査官
2003年4月 ~ 2004年3月
総務省統計研究所 客員研究官
2003年4月 ~ 2004年3月
一橋大学経済研究所 客員助教授
2001年4月 ~ 2004年3月
独立行政法人経済産業研究所 ファカルティーフェロー
2000年4月 ~ 2002年3月
獨協大学経済学部 専任講師
1998年4月 ~ 2000年3月
一橋大学経済研究所 助教授
1995年4月 ~ 1998年3月
財団法人電力中央研究所社会経済研究所 主任研究員
1995年10月 ~ 1997年10月
経済企画庁経済社会研究所 客員研究員
趣味・マイブーム/
自動車、読書

小尾晴美 助教
経歴/
2019年9月 ~ 現在
中央大学経済学部 助教
2016年4月 ~ 2019年8月
名寄市立大学保健福祉学部 専任講師
趣味・マイブーム/
旅行、散歩