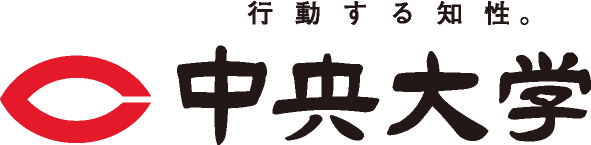【特別対談】
社会経済学科 佐藤拓也先生
多角的な視点で物事を考える力を養い
複雑な社会問題の解決に挑む
中央大学経済学部の社会経済学科で学ぶ意義を語っていただきました。
社会経済学科では何を学ぶ?
中村:
社会経済学科では、経済学の諸分野にくわえて経営学や会計学、統計学などを横断的に学び、多角的な視点で経済を分析する力を身につけます。経済学にはさまざまな立場や理論があることから、それぞれの考え方や特徴を理解していく必要があります。今日の格差や貧困といった社会問題をみても、背景には多くの要因があると考えられています。ですので、一つの事象を扱うにしても多角的な視点を養うことが求められるわけです。
佐藤:
経済学と聞くと、データを分析したり数字を扱ったりする学問というイメージを持つかもしれません。もちろんデータを読み解くことも重要ですが、社会経済学科は数字の背景にある社会の動きや、社会問題が起こる過程を考えることも大切にしています。例えば格差の問題を取り上げる際には、数字で所得水準などの現状を捉えるだけでなく、問題の背後にはどのような要因があるのか、過去の出来事や制度が関わっているのかなど、数字だけでは見えない背景まで考察します。数字が得意かどうかに関わらず、社会の動きや問題に関心がある方に、ぜひ学んでいただきたい分野です。

中村:
私が研究者を志したのも、大学生の時に起きた出来事に興味を持ったのがきっかけでした。当時、ヨーロッパでは東欧諸国がEUに加盟し、統合が進展、拡大していました。しかしその一方で、フランスやドイツでは移民に対する差別や国内の分断など、統合とは真逆とも思えるような動きも生じていました。統合が進むはずの社会で、なぜ逆の動きが生まれるのか。こうした現象の背景をもっと知りたいという思いから、ヨーロッパの統合の過程を学び始めました。現在は主にフランス経済を対象とした歴史研究をしており、労働問題や移民の受け入れといったテーマを歴史的な観点から分析しています。佐藤先生も、何かに関心を持たれたことがきっかけで、研究テーマを選ばれたのでしょうか。
佐藤:
はい、私は特定の社会問題というより、広く現代の経済状況そのものに関心があったため、現代経済や資本主義を対象に研究を始めました。専門としているマルクス経済学の理論をもとに社会の動きを考えています。一般的に企業には利益が出れば次の投資を行ったり、より多く人材を確保したりすることが求められていますが、現在の日本では利益を使わずに資金を溜め込む傾向にあります。私はマルクス経済学の階級論や利潤論の概念を手掛かりにして、投資の停滞を労働者階級と資本家階級の対立のせいと見るか、利潤を追求する資本主義社会の仕組みによるものと見るかなど、ヒントを求めて思索しています。こうした理論を手がかりに、現代の課題を経済学の理論で読み解いていくのが私の研究です。
大学の学びとはどのようなものですか?
佐藤:
私のゼミでは議論やプレゼンをする機会を多く設けており、学生にはどんな意見であれ発言は自由と伝えています。また、教員が頭ごなしに否定せず、学生の議論やプレゼンが一通り終わった後にコメントを加えるようにしています。
中村:
ゼミ運営に関しては私も同様で、自由に議論できる場をつくるようにしています。大学を離れると、組織の利害や上下関係などに左右されて発言しづらいこともあると思いますが、大学という場はそうした制約はほとんどありません。だからこそ自分の考えを十分に表現し、議論を深められる環境を整えています。
佐藤:
たしかに組織に関係なく発言できる場であるからこそ、他者の視点で物事を考えることができると思います。例えば生産者と消費者という立場の違いがあれば、商品を値上げすべきか否か意見が分かれるでしょう。学生の考えを聞く際は、あえて自分の考えと異なる意見も出してもらいます。異なる立場を意識しながら考えることで、一つの問題を多角的に捉える力が養われ、自分の意見の根拠をより明確に意識することにつながります。

中村:
おっしゃる通りです。他人の立場を理解するとともに、自分の考えを知ることも重要になります。育った環境による影響などから人は規範意識にとらわれてしまうことがあります。大学では考え方を客観的に捉え直し、「自分の考えはどういうものであるか」を知ることができます。卒業後に自分の意見を持ち、自らが所属する組織の立場を把握しながら説明する力につながるはずです。学生一人ひとりの主体性を尊重し、自ら考え、学ぶ力を育てることに重点を置いています。
誰もが働きやすい環境を考えるために
ジェンダー格差を示す指数によれば、日本は148カ国中118位に位置しています。これほど順位が低いのは、政治・経済分野での改善が遅れているとされているからです。働く女性の数は増えており、結婚や出産で仕事を辞める女性の割合は減る傾向にあります。つまり、女性の社会進出は進んでいるかのようですが、その一方でジェンダー格差に関する国際的評価はなぜ高くならないのでしょうか。この問いにアプローチするためには、一部のデータのみを見るだけではなく、経済理論や歴史など多様な観点から実証的な分析を行うことが求められます。少子高齢化が進み、労働力不足が深刻とされる今日、誰もが働きやすい制度や環境を整えることが課題の一つであると考えられます。性別、年齢、出自などの属性にとらわれず、さまざまなバックグラウンドを持つ人がともに働けるような、多様性ある社会に向けて何が必要であるのかが問われています。
社会経済学科で獲得できるスキルや知識とは?
佐藤:
社会経済学科は多角的に経済学を学ぶ学科だからこそ、さまざまな考え方で物事を考える習慣が身につきます。そのため、相手の立場や意見を理解する力が養われ、異なる考え方も受け止められるようになります。このような力は将来、他者と協働する場や議論の場で役立つはずです。
中村:
自分と異なる立場にいる他者への理解を深めるために、社会経済学科では経済理論を学ぶだけでなく、現地調査を通じて実際の声を直接見聞きすることも重視しています。海外に出て歴史研究に使う史料を集める、インタビューなどで生の声を聞くといった調査を通してこれまで気がつかなかった、社会がもつ別の側面を知ることができます。こうした体験をへて、また新たな視点で物事を考える力が育まれるのです。
佐藤:
たしかに、歴史研究の史料や現地の声など、さまざまな情報が社会問題を考えるヒントになりますね。それらを丁寧に読み込み、考え抜くことで、正解がない問題に対しても粘り強く解決を模索する力が身につきます。つまり、資料や情報を扱う力、考えを整理する力、そして発信する力が同時に鍛えられるということです。

中村:
そうですね。大学時代は、丁寧かつ論理的に思考を組み立てていく習慣を身につけてほしいと思います。こうした習慣は、自分の意見を説明し、他者と協働する力として生きてくるはずです。
登壇者プロフィール

中村千尋 准教授
経歴/
2022年4月 ~ 現在
中央大学経済学部 准教授
2017年4月 ~ 2022年3月
千葉大学大学院社会科学研究院 准教授
2015年4月 ~ 2017年3月
千葉大学法政経学部 准教授
2014年4月 ~ 2015年3月
東京大学大学院経済学研究科 助教
趣味・マイブーム/
読書、旅行
研究室のおすすめポイント/
将来を見据えて、一生懸命に研究に取り組む学生が多いこと

佐藤拓也 教授
経歴/
2021年11月 ~2025年10月
中央大学経済学部長
2012年3月 ~ 2014年3月
ブロック大学社会科学部社会学科(カナダ) 客員研究員
2012年4月 ~ 現在
中央大学経済学部 教授
2007年4月 ~ 2012年3月
中央大学経済学部 准教授
2005年4月 ~ 2007年3月
中央大学経済学部 助教授
2001年4月 ~ 2005年3月
県立新潟女子短期大学生活科学科生活福祉専攻 専任講師
2000年4月 ~ 2005年3月
中央大学経済研究所 客員研究員
1997年7月 ~ 2001年3月
日本大学経済学部経済科学研究所 共同研究者
趣味・マイブーム/
最近10年くらいフロアボール(ネオホッケー)。数年前からオーケストラでホルン担当(学生時代以来、久々に再開)。
研究室のおすすめポイント/
テーマを自由に決めて研究できること