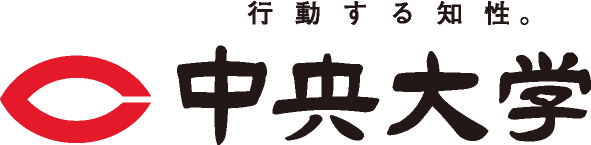【特別対談】
経済学科 小森谷徳純先生
社会問題を解決に導く、データ分析力。
物事の核心に迫る観察眼を磨け
中央大学経済学部の経済学科で学ぶ意義を語っていただきました。
経済学科で学ぶ「経済学」とは?
中村:
経済学科では、すでに世の中にある経済的理論が正しいのかを、調査や観察で得られたデータを使って調べます。現代はスマートフォンやPCなど、性能のいい情報収集ツールが多くあるので、手元にないデータでも必要なものは簡単に手に入りますが、経済学を学ぶ皆さんにはデータの信頼性や理論的整合性を検証し、判断する力を養ってほしいですね。
小森谷:
私も同感です。データを用いて既存理論を検証する手法は従来から広く行われており、新しい学問分野ではありません。ですが、中村先生もおっしゃったように、政府が公開する詳細な統計データなど、今は精度の高い情報に容易にアクセスすることが可能です。それらを的確に読み取る、いわゆる「分析力」の強化を目指し、2027年度より新しい経済学科が誕生します。2学科に改組後は、各学科で環境・国際・労働など各分野の経済理論を包括的に学べるようになります。経済学を体系的に履修したうえで、質の高いデータを用いながら理論の整合性を見極める。実践的な学びができる点が、経済学科の魅力です。

中村:
たしかにそうですね。最新ツールを活用して理論への理解を深めることで、必要なデータの洗い出しや入手したデータの信頼度を判断できるようになり、徐々にデータ分析が得意になる。それこそが我々の提供する教育のねらいです。新しいデータ収集法や分析ツールに対応できる応用力を育成するために、新たなカリキュラムも準備しています。最初に基礎的なデータの取り方を学んで、次に分野ごとの学びを深めるという一つの流れができたイメージですね。
小森谷:
4年次で関心のある分野に特化したデータ分析や、その活用方法を研究します。例えば「空間経済学」という授業では、実際に地理情報や都市データ分析の研究者が講義を担当し、研究で培った独自のノウハウに基づいて応用的なデータの使い方を直接伝授します。データ収集ツールの進化に順応できる力をもった学生を輩出するため、指導内容は学科全体で随時ブラッシュアップしていきます。
先生方の研究テーマについて教えてください。
小森谷:
国際経済の分野で、貿易をテーマに研究しています。中でも「モノの動き」と「企業の立地」の関連性に着目し、各国の経済・貿易政策が企業の海外進出に与える影響を検討しながら、進出した企業が貿易にどう関与するのかも調査しています。
中村:
私は公共経済学が専門です。社会政策を決定する立場に立って、どのようなルールを制定し、何を制限すべきか、つまり、具体的な施策についてデータを用いて考えます。今注力しているのは、インドのフードデリバリー市場で増加しているバイク事故の防止。事故による犠牲者を減らすことを目指して、どうすれば適正速度で安全に走行させられるか、また、政策を導入した際にきちんと効果を出せるかなどをインフラや交通量のデータから検証しています。小森谷先生も、世界情勢や話題のトピックについて考えることはありますか?

小森谷:
はい、世の中でリアルタイムに起こっている動きは私も授業で取り上げています。まさに今だとトランプ関税ですね。教科書の記述と違うことが起きている状況なので、「トランプ大統領の関税戦略は、教科書に載っている理論的に予測される行動にかなり近い。ただ、それは理論上のやりそうな戦略であったけど実際には実践されていなかった。それなのに今、それが目の前に…」という解説をしながら学生たちに議論を促しています。これまでと一変した経済情勢について、私自身も考えを巡らせながら授業を展開するのは非常に面白いです。これからも経済学の核となる部分は維持したうえで、学生と教員がともに新しいトピックやツールに挑んでいく環境を作りたいと思っています。
中村:
そうですね。私の専門である公共経済学は、人間の心理や予測できない行動が絡むので、心理学の要素を取り入れた行動経済学的な視点も持ちながら多角的にアプローチする必要があります。複雑ですが、それをデータで実証しようとするプロセスがこの分野の醍醐味です。正当性が漠然とした意見でも、データで根拠を示すことができれば社会を良い方向に導く提言となりうる。ここに大きなやりがいを感じています。
転売ヤーは規制するべき?高額転売の問題を経済学の視点から考える。
ライブのチケットや限定品を買い占めて、高く売ることで利益を得る転売ヤー。近頃のニュースを見ている方ならきちんと規制すべきと感じていると思いますが、実は彼らの行いは商社のビジネスと変わりありません。では、転売ヤーの何が問題なのか。彼らが非難されるのは、高すぎる値付けにより「本来消費した方が良かった人」に商品が届いていないかもしれないからです。公共経済学の視点からこの問題を検討するなら、「本来、消費すべき人に商品が届かない」というデメリットが生じる→このデメリットが社会に及ぼす影響を測る→結果を評価し、規制の要否を判断するというプロセスになります。転売は規制すべきだと直感的に考えていた人でも、経済学の視点から捉えると問題の本質がわかり、さらに考えを深めることができるかもしれません。日本では未だ適切な規制制度は整っていないので、まだまだ議論の余地がありそうです。
経済学科での学びは将来にどう活きる?
中村:
多様なデータ分析の手段を試せるので、徐々に個々の課題の特性に合わせて最適なツールを選んで使えるようになります。例えば営業職で成果を出すには、顧客やKPIなどのデータ分析を通じてより良い提案をすることが不可欠です。このときに大学で培った分析力が強い武器となるでしょう。目の前の問題を論理的に考えて、分析するために手持ちの知識を当てはめて解決に導くといった応用力が身につけられると思います。
小森谷:
企業で活かせる本学科の学びといえば、多様性への理解でしょう。経済政策と国際経済の2コースに分かれますが、いずれのコースも海外と密接にかかわり、他国の事例を学びに取り入れています。私のゼミでは毎年アジア圏の国に研修旅行をしていますが、やはり海外に行くと学生は否が応でも多様性を感じるはずです。外国を観察して、そこで得られた知見や感覚を学びに還元する過程では、新たな発見があると私自身も実感しています。自分と異なる視点を取り入れ、理解しようとすることは企業などの組織の一員として働くうえでとても大切なので、できるだけ海外には連れて行きたいですね。

中村:
なるほど。数字で測れるスキルではなく、学生ひとりひとりの人間力を伸ばすための取り組みですね。私も学生には自らで考える力を伸ばしてほしいので、授業はある程度学生の自主性に任せているのですが、ひとつだけ心掛けていることがあります。それは、「なぜ今この話題を取り上げるのか」を冒頭で明示することです。指導の目的を踏まえて、実際にアクションに起こすか否かは学生次第。行動するもしないも自分で考えてもらいたいので、例えばプレゼンまでの準備が間に合わない進捗具合だったとしても、私から働きかけることは少ないかもしれません。
小森谷:
学生の自己理解の第一歩とも言えますね。自主的に課題を進められるとか、指示されないとできないタイプだとか。
中村:
おっしゃる通りです。そういった意味でも自主性が育つ環境だと思います。
登壇者プロフィール

中村彰宏 教授
経歴/
2020年4月 ~ 現在
中央大学経済学部 教授
2012年4月 ~ 2020年3月
横浜市立大学国際マネジメント研究科 教授
2011年4月 ~ 2012年3月
横浜市立大学国際マネジメント研究科 准教授
2005年4月 ~ 2011年3月
帝塚山大学経済学部 准教授
2003年4月 ~ 2005年3月
帝塚山大学経済学部 専任講師
1996年4月 ~ 2003年3月
総務省(郵政省)
趣味・マイブーム/
筋トレ
研究室のおすすめポイント/
研究室メンバー(ゼミ生)は仲が良いです。自分たちで話し合って決めたテーマのデータ分析を助け合って勉強しています。

小森谷徳純 准教授
経歴/
2013年4月 ~ 現在
中央大学経済学部 准教授
2014年4月 ~ 2016年3月
コペンハーゲン・ビジネススクール 客員研究員
2009年4月 ~ 2013年3月
中央大学経済学部 助教
趣味・マイブーム/
趣味を作ろうとすることが趣味・思い立ったが吉日
研究室のおすすめポイント/
さまざまな挑戦の機会があること