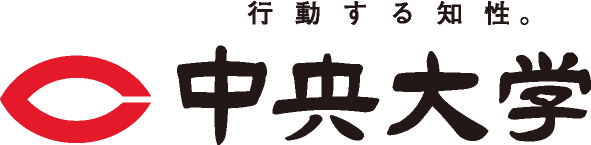Q&A
受験生のみなさんからお問い合わせの多い事項について
Q&A形式でまとめています。
学びの内容・カリキュラム
他大学の同様の学部・学科との違い(特徴や強み)は何ですか。
いずれの学科も経済学を系統的に学ぶという点が特徴です。
経済学科は、まずは全員がミクロ経済学とマクロ経済学を完全に理解したうえで、体系的な学問である経済学を、より上級の具体的なコースに分かれて、国際経済や経済政策を系統的に学んでいきます。したがって、卒業時には、自分の専門領域の基礎から応用・発展までを系統的に修得していることから、専門性が高く身に付くことになります。
社会経済学科は、ミクロ・マクロ経済学(入門)、マルクス経済学の3つの経済学をまず全員が学んだうえで、2年生以上で「地域」「経営」「社会」といった自分の興味に応じたコースを選択していきます。したがって、一口に「経済学」といっても実は多様な考え方があることをしっかり身に付けているので、そこから、問題解決にとって何が「最適解」かを導き出す力を養います。
これまでの「経済学科」と学べる内容は変わりますか。
変わります。これまでの「経済学科」では、経済学の理論(ミクロ経済学、マクロ経済学、マルクス経済学)、歴史(経済史、経済学史)、政策(経済政策、社会政策)などを幅広く学ぶことに主眼がおかれていました。新「経済学科」では、ミクロ・マクロ経済学(理論)を基礎にして、そのうえで国際経済や経済政策といった、より具体的な内容を、系統的に学んでいきます。その際に、「データ分析」の考え方も重視します。
歴史に興味があり、社会経済学科を志望しています。社会経済学科で学ぶ歴史的アプローチとはどのようなことですか。
社会問題や経済問題を、経済学の理論や数式だけで理解しようとするのではなく、そこに至る歴史的な背景も踏まえて解明しようとするものです。「物価が上昇する」ということを例にとれば、理論的には「需要と供給」の関係で説明することができますが、たとえば、第二次世界大戦終結直後の物価上昇と2020年代の物価上昇では、その背景には、資本主義社会であるという共通性がある一方で、時代によって社会情勢や経済制度・経済政策、国際関係が異なるといったように、歴史を踏まえて理解しようとするアプローチです。
経済学科での「データ分析」と社会経済学科での「統計」はどのような違いがあるのですか。
「統計」は経済や社会にかかわる状況を数量的に把握するもので、たとえば、日本の所得格差の状況を、高所得層、低所得層の分布のような形で明らかにします。「データ分析」はさらにそこから進んで、経済学科の場合であれば、経済学に関する理論的な仮説を立てたうえで、その理論がどの程度正しいかを、統計数値を用いて実証しようとします。もちろん、「統計」から「データ分析」に発展的に進むこともできますし、逆に「データ分析」の基礎にまずは「統計」が必要ということにもなりますので、実際には、両者は重なっていると言えます。
経済学科は「理論×データサイエンス」を特徴としていますが、社会経済学科に「計量経済学」や「統計・データサイエンスプログラム」があるのはなぜですか。
経済学科では、「経済学」「国際経済」「経済政策」などを学ぶときに、データ分析を併せて学びます。言い換えれば、これらの経済学をそれぞれ専門にする教員が、授業の中や、あるいは関係する授業において、データ分析についても扱うことになります。
社会経済学科では、初歩的な「統計リテラシー」を除き、統計やデータについては「選択して」学びます。必ずしも「経済学」の学びにとって全員が必須ということではありません。歴史や制度の面からアプローチする学び方もあります。
文系で、数学が苦手で社会経済学科に興味がありますが、授業に対応できますか。
経済学科と比較すると、数学が苦手な方でも学びやすいようにカリキュラムが設計されています。なお、苦手な数学に再チャレンジしたい場合は、授業科目「基礎数学」等を受講し、数学的素養を育みながら、学びを深めていただくことも可能です。
経済学科の「リアル」×「デジタル」の教育手法とは具体的にどのようなものですか。
「リアル」とは、教室での講義やディスカッションやプレゼンテーションを含む少人数の演習(ゼミ)、さらには国内外に出向いたり国内外から人を迎え入れての交流などのことを指します。「デジタル」とは、オンライン授業やオンデマンド型授業といった授業の形式、さらには国内外の諸地域とのインターネットを用いた交流、また、AIやデータなどを積極的に活用することを念頭においています。
フィールドワークとは、どのような履修で、どのようなことをするのですか。
主にゼミを履修した場合に、そのゼミの担当教員やゼミ生による計画に基づいて、実施することが多いです。具体的には、海外の現地調査(環境問題、交通問題、工場調査など)や現地の大学生との交流(プレゼンテーションやディスカッション)、国内の各地域で地域経済の調査や町おこし事業への参加、地方自治体の役所や施設(子育て支援、教育、なども含む)へのヒアリング調査など、ゼミによって多種多様なものがあります。
卒業に必要な単位数に変更はありますか。
2027年度入学生からは卒業に必要な単位数が124単位となります。
現在高校3年生です。2026年度に入学すると4学科制ですが、卒業まで同じ4学科制ですか。
2026年度入学生は、現在のカリキュラムでの入学になりますので、卒業まで4学科制のまま学修します。
進路・就職・資格
「専門性」を身に付けるとありますが、社会とどのように関係して(役立って)いますか。分析力や実践力が活用される想定例を教えてください。
経済学科が掲げる「分析力」とは、社会で出会う目の前の問題を、データ分析や理論的な考え方を駆使して、その本質は何なのか、その本当の原因や背景は何なのか、といったことを明らかにすることです。したがって、社会に出たとき、一見複雑に見える問題を的確に把握し、その解決への糸口を提示することにつながります。
社会経済学科が掲げる「実践力」とは、「最適解を導きだす」ということと表裏一体です。社会で出会う目の前の問題は、様々な捉え方や立場によって見え方が異なります。世の中には多様な考え方があるため「最適解」もそれぞれ異なる、と学んでいるからこそ、多くの視点を踏まえて実践的に解決へ向けて物事を進めていくことができるのです。
公務員の就職を希望していますが、どちらの学科がよいですか。
公務員には国家公務員/地方公務員/国税専門官等があり、目指す内容でも異なってきます。どちらの学科でも公務員への進路を目指すことは可能ですが、将来的に官公庁、地方公務員の中でもデータ分析を活かして政策立案に携わりたい人は経済学科、地域格差やマイノリティ等の諸問題を直接解決したい、または地域の企業経済や福祉等に興味があるのであれば、社会経済学科がそれぞれより近いと言えるでしょう。
金融業界の就職を希望していますが、どちらの学科がよいですか。
金融業界といっても、証券、保険、メガバンク、地方銀行等様々あり、業種も異なってきます。どちらの学科でも金融系の職種への進路を目指すことは可能ですが、将来的に、データ分析、論理的思考を活かしてキャリアを身に付けたい人は経済学科、地域経済や中小企業支援等、より実態問題に即したサポートに興味がある場合は、社会経済学科がより近いと言えるでしょう。
公認会計士の資格取得を希望する場合、どちらの学科がよいですか。
社会経済学科の地域・マネジメントコースに「経営会計プログラム(履修モデル)」が置かれています。公認会計士を目指す場合、系統履修の観点からはこちらのプログラムが最も近しい可能性があります。一方で多くの方が経理研究所に所属し、資格の取得を目指していますので、経済学科や他のコースを選択した場合でも、公認会計士への道がなくなることはありません。
教職免許はとれますか。
経済学科では中学社会・高校公民・高校商業の3教科を、社会経済学科では中学社会・高校地歴・高校公民・高校商業の4教科を課程認定申請する予定です。なお、申請の結果、課程を設置できない可能性もあります。
入試・受験
2027年度入試からの変更点を教えてください。
中央大学受験生ナビ ConnectWebの「入学試験における主な変更点」の「2027年度入学試験」をご確認ください。
各学科の定員に変更はありますか。
学部全体の定員は1062人で変更ありません。
学科定員は変更になります。現在は、経済学科467人、経済情報システム学科180人、国際経済学科が265人、公共・環境経済学科が150人です。2027年度からは経済学科:542人、社会経済学科:520人となる予定です。
キャンパスライフ・サポート
再編によりキャンパスの場所が変わることはありますか。
変更の予定はありません。経済学部は多摩キャンパスにあります。多摩キャンパスには、資料が充実した図書館、4階建ての食堂など、快適に過ごせる施設が盛りだくさんです。
学科ごとに使える施設やサポート体制に違いはありますか。
違いはありません。どちらの学科も自由に施設を利用して、勉学や課外活動に励むことができます。